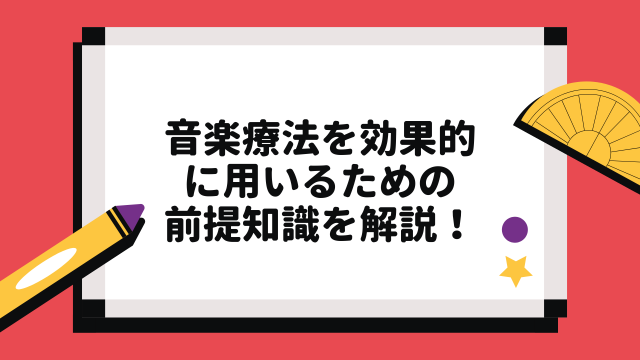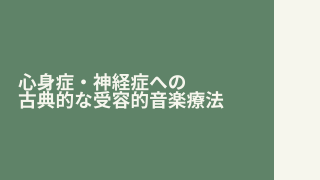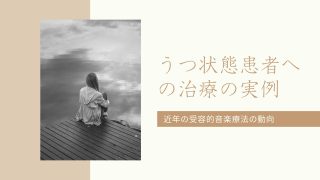音楽は人類の長い歴史の中で、ある時は感情表現の手段として、またある時は高ぶった感情を鎮静する手段として常に人類と深いかかわり合いをもって発展してきました。
音楽は人間の美的感覚を満足させ、同時に知的過程を通らずに直接情動に働きかけ、情動を調整したり、その結果として社会適応を阻外するような衝動の昇華作用を発揮します。
音楽の以上のような作用を利用し、心身の障害の回復、特に疾患の発症や経過に動の乱れが関与するような病態の治療に音楽を用いる音楽療法は、近年心身医学領域でも種々の病態に対して用いられ、その成果の報告が散見されるようになりました。
今回は、受容的音楽療法を行っていくか、古典的な受容的音楽療法に基づいてご紹介します。
調整的音楽療法とは?
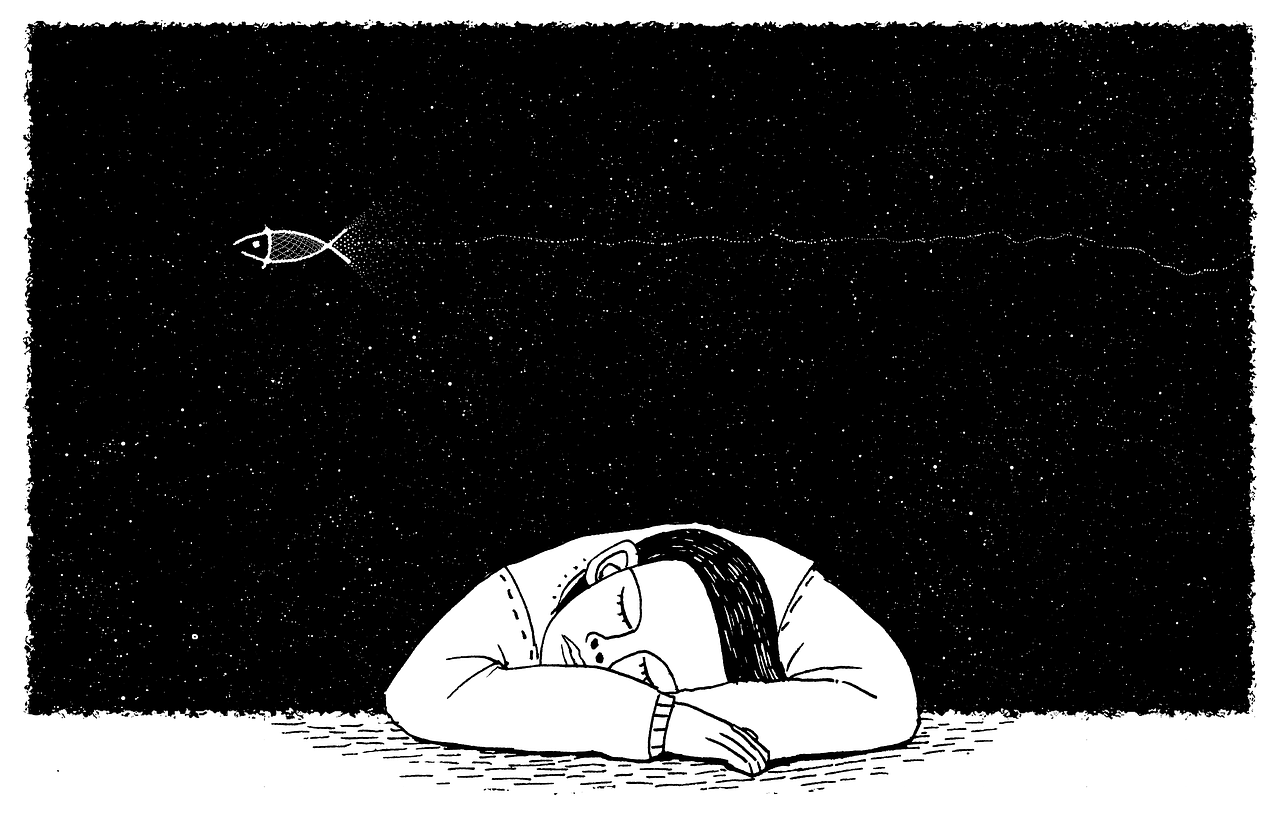
調整的音楽療法のポイント
本法はC. Schwabeにより創始された弛緩訓練の一種で、音楽を聴くことで起こる心身のリラクセーションを寄りどころにしながら、「あるがまま」「受け入れ受け流す」「客観的観察」などの精神的態度を会得していくものです。
具体的な調整的音楽療法の手順
まず患者は、やや堅い床の上に仰臥し、次いで約10分間流された音楽を聞きます。
この際、同時に体の知覚や自己の内部に起こる様々な想念にも注意を向けます。
このため、患者の注意は、聴覚、体性感覚精神内界の間を振り子様に移動します。
本法は週2回で3カ月で終了するが、全過程は4期に細分できます。
どういった曲を用いるのか
第1期は、モーツァルトのK.V.488のピアノ協奏曲の第2楽章のような、ゆっくりしたリラクセーションに適した音楽を使い、第2期はブラームスのピアノ協奏曲第2番第1楽章のようなテンポの速い曲を用い、第3期は、なじみの薄いバルトークやストラビンスキーの曲を用い、第4期では、通勤電車などで周囲の雑音を音楽に見立てて訓練が行われます。
本法は東ドイツでは広く用いられているというが、本邦では精神科領域で村井が試みた報告があります。
精神的態度を会得する

いかがでしたでしょうか。
調整的音楽療法は、音楽を聞くことで精神的態度を会得する方法となりますので、ぜひ効果的に取り入れてみてください。
他の記事でも音楽療法にまつわる知識を紹介していますので、ぜひご覧くださいませ。
最後までご覧いただきありがとうございます。